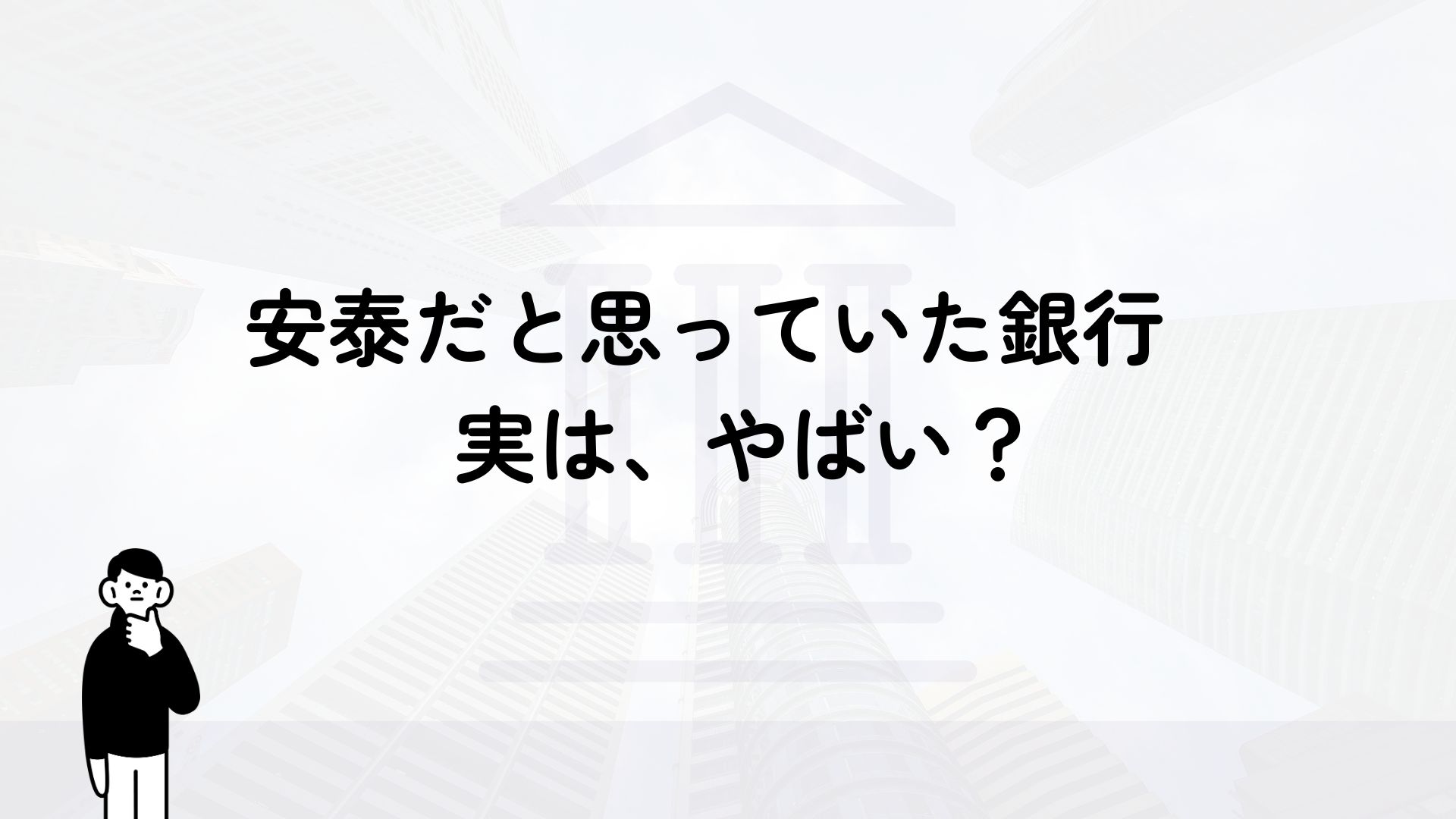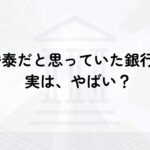変わりゆく銀行業界―「安定」の幻想とは
「銀行員は安定している」そう思われていた時代は、もう過去のものかもしれません。みずほ銀行は、今後10年間で1万9000人の削減を計画しています。三井住友銀行も、店舗統廃合を加速させています。
メガバンクでさえ、この状況です。「大きすぎて潰れない」と言われていた存在が、今、大規模なリストラと店舗削減を進めている。これが意味することは何でしょうか。
地方銀行は、さらに厳しい状況に置かれているかもしれません。
システム統合の迷走──本当に大丈夫か?
二重システムによる負担とリスク
日本カストディ銀行では、2020年の合併以降、二つの基幹システムが併存しています。この状況がもたらすのは、現場への大きな負担とリスクです。合併から3年以上が経過した今もなお、JTSBの「FMシステム」とTCSBの「NICEシステム」が並行して稼働しています。
このままでは、システム維持にかかるコストやリソースが二重にかかり、効率化を阻害しています。この二重システムは、単なる技術的な問題に留まらず、現場の士気にも影響しています。日常業務の多くがシステム対応に追われることで、顧客対応や業務改善に専念する時間が削られています。
2025年3月にはデータセンター撤退の期限が迫る中、いまだに統合方針が定まらない現実。このままでは、働く社員の負担は増し続けるばかりです。システム統合の遅れが示すのは、企業としての大きな機会損失です。
効率化が図られず、システムトラブルが続けば、競合他社との競争力を維持することも難しくなるでしょう。この現実は、「絶対に潰れない」という安定神話の裏に潜む大きなリスクを浮き彫りにしています。
データセンター撤退までの猶予はわずか
日本カストディ銀行が抱えるもう一つの課題が、データセンター撤退期限への対応です。2025年3月までにデータセンター機能を統合する必要がありますが、現状では方針が定まらず、時間だけが過ぎ去っています。これは単なる技術的な問題に見えるかもしれませんが、その影響は組織全体に及びます。
この動きが示すのは、各部署の業務負担が増大する可能性です。システムの移行に伴うトラブル対応や新体制への適応に追われる現場社員の姿が目に浮かびます。このように、管理職が取り組むべき戦略的な課題が放置され続ければ、現場のオペレーションは苦難を強いられます。
ギリギリのスケジュールで、果たして無事に計画は実行できるのか。こうした不透明な状況が続く中で、社員は何を基準に安心を見出していくのでしょうか。堅実さを求める仕事環境において、こうした揺らぎは遠からず士気を削ぎ、疑念を育む要因となることでしょう。
給与と昇進の停滞──働きがいはどこに?
年功序列の影響で若手の意欲喪失か?
日本カストディ銀行の給与制度に対して、多くの社員が抱く不満の一つが、年功序列による昇給の緩慢さです。在籍5~10年の中堅社員ですら、昇進しない限り給与が大きく増えないという声が多く寄せられています。本来ならば経験に応じて評価されるべき給与が、年次だけが基準となっている現実。
これでは、若手社員が長期的な目線で自身のキャリアを考えることが難しい状況です。その結果として、若手社員の中には早期離職を検討するケースも増加しています。加えて、「成果が報酬に反映されない」という声が多々聞かれる中では、やりがいを持ち続けることは簡単ではありません。
こうした不満が積もることで、銀行一筋が最大のリスクになりかねない、という現実を突きつけられます。
女性管理職増加の裏に隠れる課題
近年では、女性管理職の増加が進められており、女性比率は76.5%という高い数字を誇ります。しかし、その裏には新たな課題が潜んでいます。形式的に女性管理職の数を増やすだけでは、真に公平で実力のある評価制度とは言えません。
一部の声では、「女性の昇進が進んでいるように見えて、実際には偏った評価基準がある」との指摘もあります。このように、「表向き」の数字を追い求めることで、真の問題解決が後回しにされる危険性があります。女性管理職の増加という現象の裏には、管理職自体の質や、評価基準の再考が求められる必要性があるのです。
多様性が進む中で、数に翻弄されない質の向上を目指すことが、真の安定への鍵となるでしょう。
ルーティン業務の限界──やりがいの欠如
専門性よりも柔軟性が求められる職場
日本カストディ銀行では、業務の大半がルーティンワークで占められ、ジョブローテーションを通じて様々な業務に触れることができます。しかし、この制度は一見、多様な経験が積めるように思えますが、実際には専門性を深める機会を奪う結果となっています。専門性が身につかないという声が多く聞かれ、キャリア形成の足かせとなっているのが現状です。
この影響から、社員は「事務の会社」という評価を受け入れざるを得ません。柔軟性が求められる職場である一方で、それが自身の技能や専門的価値を薄めることにつながっては、本末転倒と言えるでしょう。本当に必要なスキルが何なのかを問い直し、充実したキャリアを描けるか否かがカギとなるのです。
「事務の会社」であることへの評価と不満
日本カストディ銀行が「事務の会社」であると言われる背景には、業務の大半がルーティン業務であるという実態があります。これによって、社員は特定の専門スキルを高めることよりも、日常の業務を効率よくこなすことを求められます。しかし、このフィードバックループの中で社員が得るものは何でしょうか?
自身の能力を磨く場と言うよりは、現状の維持を何よりも優先する姿勢が浮き彫りになります。その結果、ルーティン業務に飽きたらず、新たなチャレンジを志す社員が増えています。キャリアを形成する中で、やはり「やりがい」が得られない職場というレッテルが、その後の離職率の高さに繋がっているのです。
これは単に企業の特色に留まらず、社員自身の人生を考え直すきっかけともなり得ます。安定した現状に甘んじるのではなく、将来に向けた選択が問われる時代に突入しています。
安定性の裏側に潜む課題──本当に安泰なのか?
離職率が示す現実
日本カストディ銀行では、採用10年後の継続雇用割合が男性27%、女性40%と、離職率が高いことが露呈しています。この数字は、社員が長期にわたるキャリアを築く上で、どれほどの不安を抱えているかを示すものです。多くの若手社員がキャリア序盤で転職を考える背景には、給与や業務への不満が根深く影響しています。
このように、見かけ上の安定性とは裏腹に、社員が感じる居心地の悪さや将来への不安が如実に現れるのが離職率です。離職者数が増えることで、組織全体の安定に影を落とし、業務効率にも悪影響が生じる可能性が否定できません。この銀行が本当に安泰であるか否かを問う際に、離職率が一つの警鐘を鳴らしていることは間違いないでしょう。
経営統合後の社内カルチャーの変化
2020年の経営統合以降、日本カストディ銀行の社内カルチャーは大きな変容を遂げています。合併によるカルチャーの違いは、現場に混乱をもたらし、対応年数が長い社員にほど精神的負担を与えています。現在、部課長が親会社からの出向者で占められており、プロパー社員の不満が募っています。
こうした状況は、社員一人一人が組織に対する帰属意識を失いつつある証拠でもあります。これは、組織全体の活力を削ぎ、結果的に企業としての競争力を低下させる結果につながる危険性を孕んでいます。このままでは、社内の不均衡が拡がり、企業全体の足かせとなる可能性があるのです。
「安定」を守るためには、むしろ変化と向き合うことが必要な局面にあると、強く印象付けられます。以上の現実を踏まえた時、「日本カストディ銀行は本当に安泰なのか?」という問いが社員の心に響くことでしょう。安定を求めて入った組織で、いま問われるのはその「安定」がどのように保たれ、どのように迎えるべき変化を進めるかです。
読者の心に、こうした疑問と共に新たな認識を育むきっかけとなれば幸いです。
では、どうすればいいのか?
銀行一筋は大きなリスクを伴う時代です。収入源を多様化することが重要。でも、「どうやっていいのか分からない」AI副業とか聞くけど、具体的に何をすればいいのか。
その気持ち、よく分かります。実は、私はこれまで2000人以上の方の相談に乗ってきました。みなさん、同じような悩みを抱えていました。
「何から始めればいいのか」「自分にできるのか」「失敗したらどうしよう」でも、一歩踏み出した人たちは、確実に変わっていきました。LINEでは、私が実際にやってきた方法を具体的にお伝えしています。押し売りではなく、あなたの状況に合わせた提案をしたい。
まずは話を聞いてみませんか?

 LINE@に登録後で登録することも可能です!
メルマガもLINE@もダブルで登録するのがオススメです!
全て同じメルマガの登録フォームとなっておりますので、ご安心くださいませー
LINE@に登録後で登録することも可能です!
メルマガもLINE@もダブルで登録するのがオススメです!
全て同じメルマガの登録フォームとなっておりますので、ご安心くださいませー