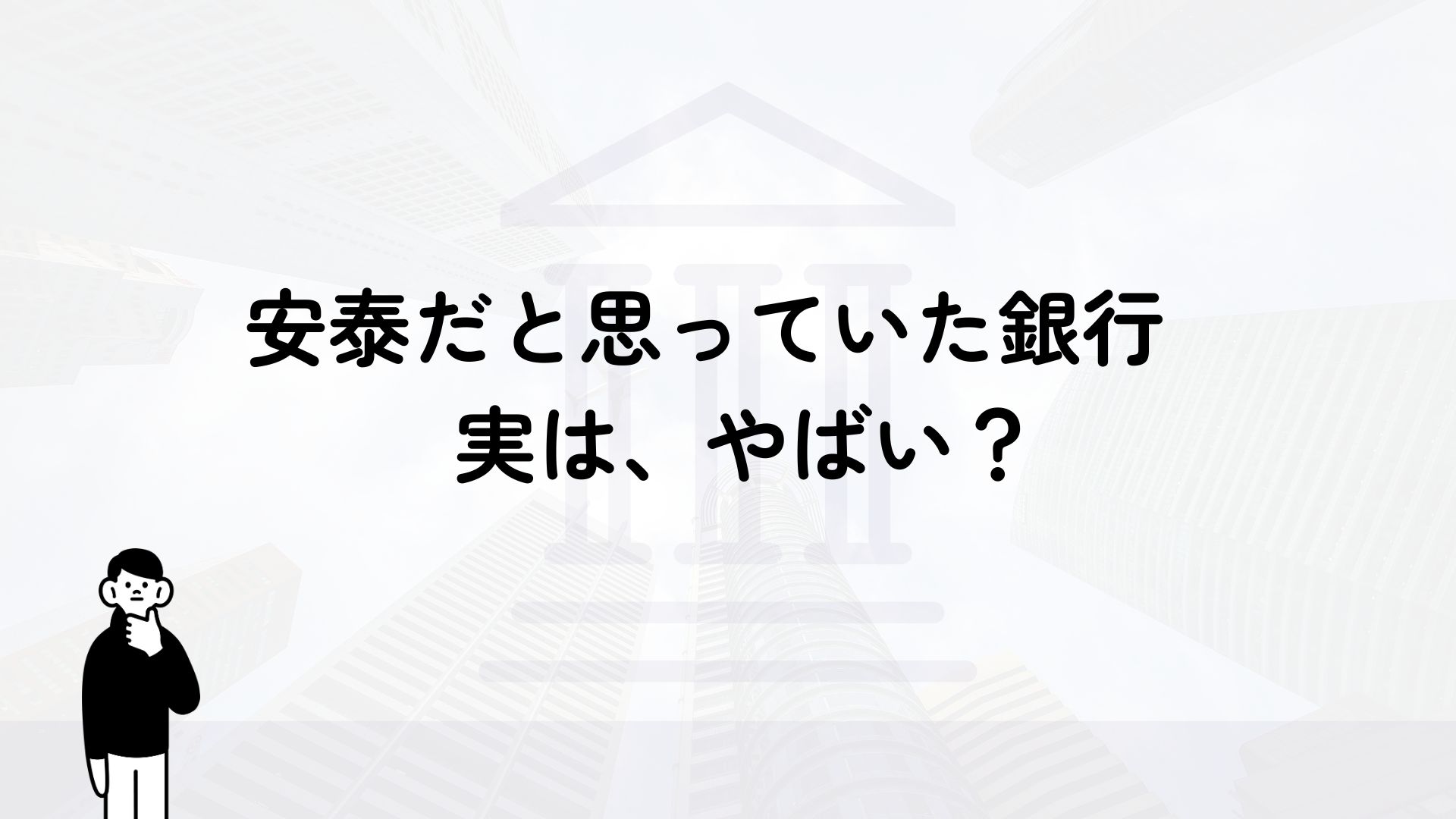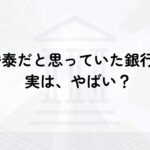変わりゆく銀行業界―「安定」の幻想とは
「銀行員は安定している」そう思われていた時代は、もう過去のものかもしれません。みずほ銀行は、今後10年間で1万9000人の削減を計画しています。三井住友銀行も、店舗統廃合を加速させています。
メガバンクでさえ、この状況です。「大きすぎて潰れない」と言われていた存在が、今、大規模なリストラと店舗削減を進めている。これが意味することは何でしょうか。
地方銀行は、さらに厳しい状況に置かれているかもしれません。
給与は本当に満足できる水準か?若手行員の実態に迫る
「給与が圧倒的に少ない」との声、その背景は?
清水銀行で働く行員の間で、給与への不満が多く寄せられています。平均年収は有価証券報告書によると616.5万円ですが、これには管理職を含むため、若手行員の実際とは乖離しているようです。ある口コミでは、4年働いても年収が350万円程度だと言われています。
この差は、表面上のデータだけでなく、職場内での実感としても広く認識されている問題です。この背景には、給与の基本給が低く、資格昇格による昇給が難しいことがあります。口コミによれば、資格を取らなければ毎年の昇給もほとんどない状況です。
これにより、若手行員が成長するためのインセンティブが不足している状況が伺えます。このような成長機会の欠落は、将来的なキャリア形成に不安を与えます。
若手行員の給与と他行比較で見る、驚きの差
さらに他の地銀との比較でもその差は浮き彫りになります。静岡銀行の平均年収は約650万円、スルガ銀行は約600万円と言われており、清水銀行はこれらに及ばない水準です。この差は、静岡やスルガといった銀行がより競争力のある給与体系を提供していることを示唆しています。
特に県内の他金融機関と比較しても低いという指摘が多く、初任給ですら苦しいという声もあります。新たな人材を獲得し、維持するためにも、給与の見直しが急務であることは明白です。しかし、現状では、清水銀行における給与の改善の兆しは見えず、このままでは優秀な人材が競合へと流れてしまうリスクを孕んでいます。
地域密着の清水銀行、競争激化の中で勝てるのか?
静岡銀行・信用金庫など強豪ぞろいの競争環境
清水銀行が直面しているのは、厳しい競争環境です。県内には静岡銀行という圧倒的な存在がおり、店舗数や総資産でも大きな差があります。加えて、スルガ銀行や地域密着型の信用金庫も競争を激化させています。
特に、静岡銀行の存在は大きく、地元の大手中堅企業との取引で優位に立っています。清水銀行は「小回りでは信金に勝てない」との声もあり、規模の面でも不利な状況にあります。このように、地域密着を強みに持つ清水銀行ですが、競争に打ち勝つための明確な戦略が見受けられません。
地域密着の重要性が薄れる中で、競争に打ち勝つ道筋を見いだせない状態です。
SBIホールディングスとの提携は救世主になるか?
清水銀行は2020年2月、SBIホールディングスと資本業務提携を結びました。これは、新たな事業機会と収益基盤の強化に繋がることを期待されていましたが、その効果は限定的です。SBI側が地銀連合への関心を失いつつあるとの指摘もあり、期待されたシナジー効果が実現できていない可能性があります。
また、情報技術やデジタル金融分野での協力が期待されていますが、デジタル化の遅れが指摘される現状では、この提携により即効性ある効果を期待するのは難しいです。提携の名のもとで希望が語られる中、現実とのギャップが埋まっていないことも、清水銀行が直面している現実です。
離職率と人間関係、裏で何が起きている?
離職率が高い理由を明らかに
清水銀行では3年以内に3割以上が辞めているといわれ、これも懸念材料です。この背景にあるのは、給与の低さや昇進機会の不足だけでなく、人間関係や職場環境も大きく影響しているようです。口コミでも「支店長の裁量が大きい」ことや「パワハラ」的行動への不満が多く寄せられています。
支店長の権限が大きく、支店ごとに職場環境が異なるため、個々の人事や日常業務が不安定になりやすいです。これが原因でストレスを感じ、離職者が増加している可能性があります。こうした職場の不安定要素がある中で、長期的に勤務することへの魅力が薄れてしまいます。
優秀な人材が長く留まることが難しい環境といえるでしょう。
支店長の裁量が大きすぎる?組織体質の実態
この環境で注目されるのが、組織のトップダウンの体質です。支店長が大きな権限をもつことで適切な運営がされる一方で、個々の支店で独自の問題が生じることもあります。「支店長次第で全てが決まる」という状況が多くの支店で見られ、このような組織体質が改善されない限り、根本的な改革の道のりは険しいといえます。
この組織の硬直性が、開発や提案の自由度を制限し、結果としてデジタル化の遅れにも直結しています。トップダウン型の限界が、組織全体を覆っているのです。
デジタル化の遅れは致命的か?未来を見据えた戦略とは
「昭和の古い体制」がもたらすデジタル化の遅れ
昨今の金融機関にとってデジタル化は避けて通れない道です。しかし、清水銀行は「昭和の古い体制」とされ、紙文化から抜け出せない現状が指摘されています。この遅れは、既存のシステムの老朽化やデジタル人材の不足、さらには投資の限界にも影響を及ぼしています。
特にオンライン化の遅れは顧客体験に直接影響し、若年層の取り込みにも支障をきたしているのが現状です。こうした遅れが続けば、金融市場での競争力を大きく欠くことになります。昭和の呪縛から抜け出さない限り、未来に向けた道筋が立てられないのです。
ユーザー不満が示す、アプリ活用の課題と可能性
現在、清水銀行の提供するアプリはその利便性において低い評価を受けています。これまでアプリを通じたサービス向上の取り組みは多少行われているものの、顧客からの満足は得られていないようです。このような状況では、従来の顧客基盤を維持することが難しいのは明らかです。
目指すべきは、より高効率で顧客に優しいデジタルサービスですが、現状ではデジタル化の取り組みが追いついていません。目の前の課題にしっかりと向き合わなければ、今後の顧客離れにつながる危機も潜んでいます。以上のように、清水銀行が直面している問題は多層的です。
給与の不満、競争の厳しさ、職場環境の課題、そしてデジタル化の遅れ。これらは単なる個別の問題ではなく、組織全体の安定性を揺るがしかねない要因です。果たして、本当にこの銀行は安泰なのか—その答えを見つけるには、読者自身がこれらの現実をどう捉えるかにかかっています。
では、どうすればいいのか?
銀行一筋は大きなリスクを伴う時代です。収入源を多様化することが重要。でも、「どうやっていいのか分からない」AI副業とか聞くけど、具体的に何をすればいいのか。
その気持ち、よく分かります。実は、私はこれまで2000人以上の方の相談に乗ってきました。みなさん、同じような悩みを抱えていました。
「何から始めればいいのか」「自分にできるのか」「失敗したらどうしよう」でも、一歩踏み出した人たちは、確実に変わっていきました。LINEでは、私が実際にやってきた方法を具体的にお伝えしています。押し売りではなく、あなたの状況に合わせた提案をしたい。
まずは話を聞いてみませんか?

 LINE@に登録後で登録することも可能です!
メルマガもLINE@もダブルで登録するのがオススメです!
全て同じメルマガの登録フォームとなっておりますので、ご安心くださいませー
LINE@に登録後で登録することも可能です!
メルマガもLINE@もダブルで登録するのがオススメです!
全て同じメルマガの登録フォームとなっておりますので、ご安心くださいませー