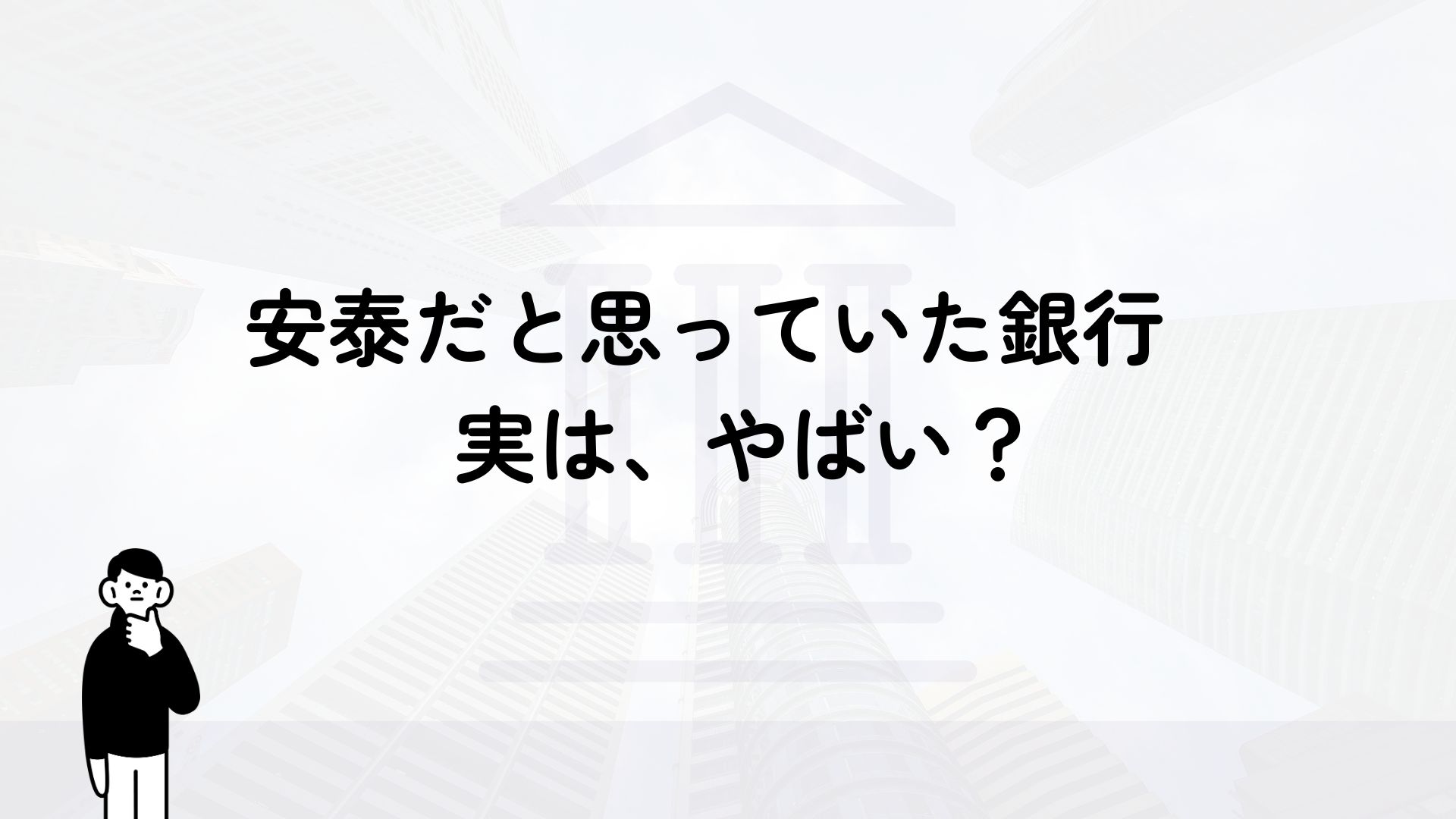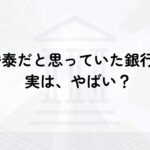変わりゆく銀行業界―「安定」の幻想とは
「銀行員は安定している」そう思われていた時代は、もう過去のものかもしれません。みずほ銀行は、今後10年間で1万9000人の削減を計画しています。三井住友銀行も、店舗統廃合を加速させています。
メガバンクでさえ、この状況です。「大きすぎて潰れない」と言われていた存在が、今、大規模なリストラと店舗削減を進めている。これが意味することは何でしょうか。
地方銀行は、さらに厳しい状況に置かれているかもしれません。
赤字脱出の目処なし?—3期連続赤字が影を落とす現状
みんなの銀行は設立以来、3期連続で赤字を計上しています。2024年3月期の最終損失は93億円に上り、累積損失は260億円に達しています。開業当初設定した「3年目で単年度黒字化」という目標も、未達成のままです。
一見、デジタルバンクとしての新規性が高く評価される中、長期的な収益性には大きな課題があります。銀行業は本来、安定した収益を前提に選ばれるもの。しかし、連続赤字が続くと、「この銀行で働くことが安定なのか?」という疑念が頭をよぎるのも無理はありません。
財務の不安定さは、しばしば職場の雰囲気や働き方に影響を及ぼすものです。そして、この影響が与える不安は、従業員だけでなく顧客にも波及する可能性があります。安定した未来を描くはずの職場が、実際は不透明な見通しの中にある。
顧客満足度に潜む問題—デジタルネイティブ世代でも使いにくい?
みんなの銀行は、ミレニアル世代・Z世代をターゲットに、スマホでの手続き完結を追求してきました。しかし、公式アプリの評価はApple Storeで3.2、Google Playでは2.9と低評を受けています。特にビデオ通話による本人確認がうまくいかないという声が目立ちます。
デジタルネイティブに向けたサービスが期待に応えられていない現状があります。数多くの新しいサービスが市場に登場する一方で、技術的な問題が解決されないと、それは顧客に対して信頼欠如を生むことになります。ユーザー体験が悪化することで、顧客満足度は下がり、そのままフィードバックが悪化のスパイラルを招きます。
これはデジタルバンクの強みを損なうものであり、戦略的な再考が求められます。
デジタル化の逆風—斬新なシステムが抱える盲点
みんなの銀行は世界初のフルクラウド型銀行システムを導入しています。しかし、その斬新さゆえにシステムの不安定さや通信の遅延が指摘されています。格安スマホや低速通信環境ではストレスを感じることも少なくないようです。
最先端の技術が必ずしもすべてのユーザーに適応するわけではありません。銀行の信頼性は、何よりも安定性にあります。技術的な革新は賞賛されるべきですが、それが安定的に運用されなければ信頼を損なう結果となります。
特に金融機関では、ユーザーの信頼感は取引の根幹を支えるものであり、挙動の不安定さは少なくとも改善が急務です。
革新的なシステムも、それが安心を提供できない限り不安の種になりうる。
収益モデルの危うさ—若年層ターゲティングの落とし穴
みんなの銀行の顧客の7割が30代以下である一方で、カードローンの残高は期待通りに積み上がっていません。既存の審査モデルが若年層のニーズにフィットしていないことが原因として挙げられます。
若年層をターゲットにした戦略は、長期的な顧客育成にはつながり得ますが、即時の収益には結びつきづらいことが明らかになっています。
この層は、必ずしも銀行からの借入を好むわけではなく、他の金融サービスに流れることも少なくありません。収益源が限られる中でのこの現実は、銀行の事業モデルそのものを再検討する必要性を示唆しています。
銀行一筋が安定の保障とは限らない今、自らのキャリアパスにも柔軟性が求められる時代だということ—その現実を疑う余地はないのかもしれません。
みんなの銀行は、デジタルバンクとしての革新性を持ちつつ、その成長を支える基盤が揺らいでいる現状があります。顧客と従業員に残されるのは、果たしてこのままでいいのかという問い。きっとその答えを見つけるのは、自分自身の選択を問い直すその一歩にあるのでしょう。
では、どうすればいいのか?
銀行一筋は大きなリスクを伴う時代です。収入源を多様化することが重要。でも、「どうやっていいのか分からない」AI副業とか聞くけど、具体的に何をすればいいのか。
その気持ち、よく分かります。実は、私はこれまで2000人以上の方の相談に乗ってきました。みなさん、同じような悩みを抱えていました。
「何から始めればいいのか」「自分にできるのか」「失敗したらどうしよう」でも、一歩踏み出した人たちは、確実に変わっていきました。LINEでは、私が実際にやってきた方法を具体的にお伝えしています。押し売りではなく、あなたの状況に合わせた提案をしたい。
まずは話を聞いてみませんか?

 LINE@に登録後で登録することも可能です!
メルマガもLINE@もダブルで登録するのがオススメです!
全て同じメルマガの登録フォームとなっておりますので、ご安心くださいませー
LINE@に登録後で登録することも可能です!
メルマガもLINE@もダブルで登録するのがオススメです!
全て同じメルマガの登録フォームとなっておりますので、ご安心くださいませー